【速報】フリーランス法違反に関する勧告事案を踏まえた企業の今後の実務対応

弁護士
高橋 尚子

弁護士
近澤 璃希

IPO準備においては、その時のトレンドに合わせて労務管理の勘所が変化していきます。最近では特に、「過重労働」や「ハラスメント」「未払賃金請求」などといったワードが人事労務の分野を賑わしています。昨今のIPO準備では、これらの問題が発生しないような万全な労務管理体制を構築する必要があります。 IPO準備では、まず、労務デューディリジェンス(労務DD)で違法性があると考えられる労務管理上の課題や上記のような諸問題の発生可能性が高い課題を明らかにすることが効果的です。 本連載では、労務DDで明らかになることが多い労務の課題とその注意点を解説していきます。初回となる今回は、論点の概要と、未払い残業代の発生原因になり得る点で重要な「労働時間管理」について解説します。

目次
2019年から働き方改革関連法が順次施行されており、また、その後も育児介護休業法や労働基準法の改正などもあり、ここ5年ほどで企業の労務管理を取り巻く環境は時代に合わせて大きく変化しています。
IPO審査では、このような労働関連法令の遵守はもちろん、その時の個別労働紛争の状況やニュース等、世の中の動きに合わせて、審査の粒度が変化しているように感じます。
最近では「過重労働」、「ハラスメント」や「未払賃金請求」などといったワードがニュースで取り上げられることが多いことから、IPO準備においても重要視される項目になっています。
このように、IPO審査を通過するためには、IPO特有の対策が必要になりますが、労務DDで明らかになることが多い重要な労務の課題は主に次のとおりです。
①労働時間管理
②労働時間制度
③労働基準法上の管理監督者
④未払賃金の把握と清算
⑤長時間労働(36協定の上限時間管理)
これらの各課題項目ついて、それぞれに関係する法令や判例などを確認しながら、IPO準備で適切だと考えられる対応を、連載で解説します。
初回となる今回は、①の労働時間管理について見ていきましょう。
労働時間管理体制の構築は、最も重要なIPO準備項目の1つです。労働時間管理が重要と考えられる理由は2つあります。1つは、労働時間管理が不適切であると、それが未払賃金の発生原因になること。もう1つは、同様にそれが長時間労働の温床になることです。
労働時間管理が適切になされないと、未払賃金や過重労働による過労死といった重大な法令違反(労働問題)の発生可能性が高くなります。
重大な法令違反はIPOスケジュールに影響することもあるため、法令違反が生じないように労働時間管理を徹底することが重要です。
ちなみに、IPO準備においては、例えば下記のような質問に回答する必要があるため、この点からも労働時間管理の重要性がうかがえます。
「勤怠の管理方法(労働時間の記録、管理職における承認、人事担当部署における管理の方法を含みます)及び未申告の時間外労働の発生を防止するための取組みについて記載してください」
日本取引所グループ「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)記載要領」より一部抜粋
「長時間労働防止のための取組について記載してください」
(新規上場申請者に係る各種説明資料)
「勤怠の管理方法及び未申告の時間外労働(いわゆるサービス残業)発生防止のための取組」
「長時間労働の防止のための取組」
労働時間管理体制は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省平成29年1月20日策定)」(以下「ガイドライン」といいます。)を基に構築します。
IPO準備上、このガイドラインで特に重要な論点は次の2点です。
1 労働時間の考え方
2 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
「労働時間の考え方」は、どのような時間が労働時間になるのかといった問題です。
もう少し踏み込むと、具体的な業務に従事しているといえるのかが、必ずしも明らかではない時間は「労働時間」に含むのかどうかという問題です。
判例では「労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいう」とされています (平成12年3月9日最高裁第一小法廷判決 三菱重工長崎造船所事件)。
また、ガイドラインでは、次のような時間は労働時間になるとされています。
これらの時間の一部は労働時間か否かの判断が極めて困難なこともあり、労務DDの結果、これらの時間が適正に労働時間として把握されていないとされるケースも散見されます。
労働時間の把握不備は未払賃金の発生原因にもなるため、IPO準備では、労働時間性を適切に判断してガイドラインを遵守し、未払賃金を発生させない労働時間把握体制の構築が求められます。
IPO準備において労働時間性の判断が問題になる例は次のとおりです。
着替え時間については、最近も、郵便局の制服着替えが労働時間であるとして、日本郵政に対し約320万円の支払を求めた判決(2023年12月22日神戸地裁判決)があり、ニュースにもなっているため要注意です。
IPO準備では、まず、このような時間があるか否かを把握し、つぎに、弁護士や社労士などの専門家の見解を踏まえて労働時間性の有無を判断しながらその取扱いの検討を進めることが効果的といえます。
この措置では、「労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること」が求められています。また、記録の方法として次の2つが定められています。
〇原則的な方法
〇やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合
ガイドライン上は自己申告の方法を認めていますが、タイムカードによる記録、パーソルコンピュータ等の電子計算機器の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法によることが原則であり(労働安全衛生法第52条の7の3第1項)、自己申告による把握のみにより労働時間の状況を把握することは、労働時間の状況を客観的には把握する手段がない場合に限られるとされていることに留意が必要です(平成31年3月29日基発0329第2号)。
IPO準備では、勤怠管理システムによる始業終業時刻の打刻に加え、PCログなどにより始業打刻前と終業打刻後の労働の有無を確認する体制が求められることがほとんどです。ガイドライン上は例外的ながらも自己申告が認められるシーンもあると考えられますが、自己申告による労働時間管理体制のまま上場審査を迎えるケースは少ないようです。
上記の「労働時間の考え方」同様に、IPO準備に長けた社労士や弁護士などの専門家のアドバイスを受けながら管理体制を構築することが効果的です。
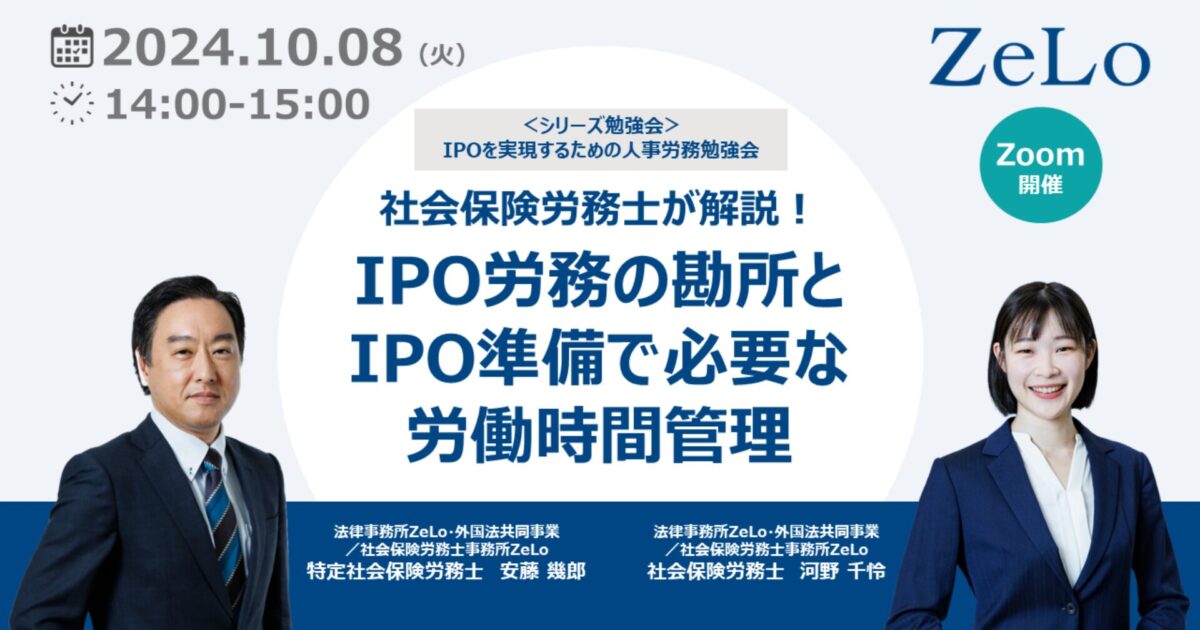
法律事務所ZeLoでは、IPOを見据えているベンチャー・スタートアップ企業の皆様に向けた、人事労務のシリーズ勉強会「IPOを実現するための人事労務勉強会」を定期開催してまいります。
第1回目は2024年10月8日(火)14:00~開催されますので、より深く勉強されたい方は、ぜひお申込みいただきますと幸いです。
※終了しました
スタートアップ企業が上場をするためには、株式会社東京証券取引所および証券会社が行う上場審査において承認を受ける必要があります。しかし、上場審査事項は多岐にわたり、申請を目指す企業での作業量が多いうえに、専門的な知識なども必要なため、難航する企業も少なくありません。万が一体制が不十分だった場合、上場審査が通らないこともあるため、前もって上場審査に備える必要があります。
社会保険労務士事務所ZeLo・法律事務所ZeLoでは、上場会社の労務管理、スタートアップ・ベンチャー企業のIPO審査に向けた労務DDの経験など、IPO審査について多くの知見を有する社会保険労務士・弁護士などの専門家が、適切にサポートします。
個社のニーズやビジネスモデルに応じて、アドバイスを提供していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

