前人未到のWeb3領域。共に開拓し、挑戦し続ける「戦友」 – 株式会社Ginco

弁護士
長野 友法

弁護士、パブリックアフェアーズ部門統括
官澤 康平
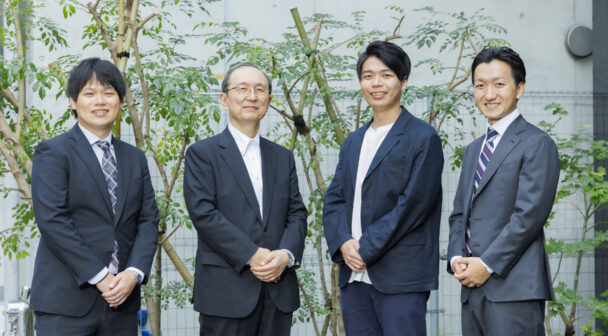
2025年6月6日、資金決済に関する法律の一部を改正する法律(2025年資金決済法改正、以下「本改正」といいます。)が成立しました。本改正では、新たに「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」に関する規律が導入されます。これにより、既存の電子決済手段等取引業や暗号資産交換業とは異なる枠組みで、利用者保護と市場の健全な発展を両立させることが狙いとされています。本稿では、改正の概要とその背景、他制度との相違点を整理するとともに、事業者が注視すべき今後の動向を解説します。

目次
本改正により、資金決済法において、新たに「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」(以下単に「仲介業」といいます。)が創設されました。
電子決済手段等取引業及び暗号資産交換業(以下、これらを総称して「暗号資産交換業等」といい、電子決済手段及び暗号資産を総称して「暗号資産等」と、電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者を総称して「暗号資産交換業者等」といいます。)よりも登録要件等が緩和された仲介業の登録を受けることで、暗号資産等の取引の媒介を行うことが認められ、ブロックチェーンゲームやアンホステッドウォレットを提供するWeb3事業者が、暗号資産交換業者等と利用者をシームレスに仲介できる環境が整います。
本改正についての議論が行われた金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」報告書*1にも記載されているとおり、Web3ビジネスにおいては、例えばブロックチェーンゲームなどのサービスの利用に暗号資産等が必要となることが多く、そのため、Web3サービスを提供している事業者が、暗号資産交換業者等が開設する販売所又は取引所に利用者を仲介し、暗号資産等の取引を可能にするケースが見られます。
この際、たとえば、(暗号資産交換業者のウェブサイトに遷移せずに)当該サービス画面上で暗号資産の購入・売却を可能にする仕組みは、「暗号資産交換業者・利用者間の契約の成立に尽力する」ものとして、暗号資産の取引の「媒介」(資金決済法2条15項2号)に該当し、暗号資産交換業等の登録が必要とされていました。
暗号資産交換業等は登録要件として財務要件が課され、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」といいます。)上のAML/CFTに関する義務も負うところ、Web3サービスを提供する企業がスタートアップ企業等である場合、これらの企業が暗号資産交換業等の登録を受けることはハードルが高いのが実情でした。そのため、暗号資産交換業等の登録を受けることなくWeb3サービスを提供する事業者も多いところ、その場合、上記のように暗号資産の取引の「媒介」に該当することを回避するためには利用者が取引するたびに暗号資産交換業者等の外部サイトに遷移する必要があり、UI/UX上の課題となっていました。
このような取引の「媒介」のみを行う者に対して、財務要件や犯収法上の義務が課されるフルパッケージの暗号資産交換業者等の登録を求めるのは、リスクに応じた規制とはいえず、過剰であるという指摘もありました。
このような背景から、規制緩和の要望も実務上多く、今般の改正により、新たな仲介業制度が導入されるに至りました。
暗号資産等の取引の「媒介」のみを行う仲介業は、以下のとおり、暗号資産交換業等に比べて登録要件が緩和され、また、犯収法上のAML/CFTに関する義務及び取引時確認義務(KYC義務)を負わないものとされていますが、その他の規制は、基本的に暗号資産交換業者等に課される規制が踏襲されています。
仲介業は、以下のとおり、本改正法2条18項において定義されています。
(定義)
第2条
1~17 (略)
18 この法律において「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段仲介行為」とは、第一号に掲げる行為をいい、「暗号資産仲介行為」とは、第二号に掲げる行為をいう。
一 電子決済手段等取引業者以外の者が、電子決済手段等取引業者の委託を受けて、電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の媒介を当該電子決済手段等取引業者のために行うこと。
二 暗号資産交換業者以外の者が、暗号資産交換業者の委託を受けて、暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介を当該暗号資産交換業者のために行うこと。
暗号資産と電子決済手段は、価値を裏付ける資産の有無等の点において異なりますが、本改正では、以下のような点を踏まえて、電子決済手段仲介行為・暗号資産仲介行為について、登録が一本化されました。
次に、仲介業の具体的な登録要件は以下のとおりです。なお、登録が一本化されたことから、暗号資産・電子決済手段いずれを取り扱う場合であっても登録要件は同じです(もっとも、登録は一本化されるものの、いずれか一方のみを取り扱う前提で仲介業者の登録を受けた者が、後から他方も新たに取り扱おうとする場合には、変更登録を受けなければならないことに注意が必要です。)。
後記のとおり、仲介業においては利用者財産の預託が禁止されているため(本改正法63条の22の13)、利用者財産の管理等の不備によって利用者に損害を与え、損害賠償責任を負うリスクは限定されていることに加え、所属制の下では、所属先の暗号資産交換業者等(仲介業者が委託を受ける暗号資産交換業者等)が基本的に利用者に対して賠償責任を負うことから、財務要件をもって万が一の際の利用者保護を図る必要がないため、かかる要件は課されていません。
また、仲介業者自身は認定協会には加入しないところ、所属先(委託元)の暗号資産交換業者等を介して、認定協会の自主規制規則を実質的に仲介業者にまで及ぼすことを想定し、所属先の暗号資産交換業者等の認定協会への加入が別途要件となっています(改正資金決済法63条の22の5第1号ハ)
その他の登録要件については、基本的には暗号資産交換業等の登録要件(改正資金決済法62条の5第1項、63条の5第1項参照)が踏襲されています。
なお、暗号資産交換業等の登録要件には組織形態要件があり、暗号資産交換業等を営む者は株式会社(又は外国電子決済手段等取引業者・外国暗号資産交換業者)である必要がありますが、仲介業は個人であっても登録が可能となっているため、上記⑨⑩のように、登録主体によって一部要件が異なっています。
仲介業者が暗号資産等の取引の媒介を行う場合、暗号資産交換業者等が当該取引に伴う AML/CFTの義務を履行しているため、仲介業者に二重に犯収法に基づく取引時確認義務を課す必要はないものと考えられることから、仲介業者は、犯収法上の「特定事業者」(犯収法2条2項各号)に加えられず、犯収法上の取引時確認義務も課されませんでした。
そのため、仲介業者による仲介行為に際して犯収法上の取引時確認は不要です。
仲介業者は暗号資産交換業者等と異なり、自らが暗号資産等の売買・交換の当事者となることがないため、利用者から金銭等を預かる必要がありません。むしろ、金銭等を預かることを認めた場合、流用等によって利用者に損害を与える等のリスクが生じる懸念があります。
そのため、仲介業においては、その名目を問わず、仲介業に関して、利用者から金銭その他の財産の預託を受けることが禁止されています(改正資金決済法63条の22の13)。
「所属制」とは、仲介業者を特定の金融機関等に所属させ、当該金融機関の指導・監督を通じて利用者保護を図る制度で、例えば、金融商品仲介業者、銀行代理業者等には所属制が採用されています。
仲介業は、個人や株式会社以外の法人による登録も認められ、上記のとおり、財務要件が課されていない等、暗号資産交換業者等に比べて参入基準が緩和されているところ、質の低い仲介業者の行為により利用者の利益が損なわれると、制度全体の信頼が損なわれる懸念があります。
そこで、信頼性を確保し、利用者保護を図るため、仲介業においても所属制が採用され、仲介業者が利用者に加えた損害について、より賠償力のある所属先の暗号資産交換業者等に損害賠償責任を負担させることとされています(改正資金決済法63条の22の14)。
なお、所属先の暗号資産交換業者等は、仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う仲介行為について利用者に加えた損害の発生の防止に努めたことを証明すれば、上記損害賠償の責任を負わないものとされています(同条ただし書)。
現在、仲介業の具体的な登録手続等を定める政令及び内閣府令の策定が当局において進められているものと考えられます。上記政令及び内閣府令が施行され次第、登録手続の受け付けの開始も始まる見込みであり、これらの策定及び施行に関する動向に注視が必要です。
法律事務所ZeLoでは、ブロックチェーン・暗号資産の流行前からその潜在性に注目して研究・実務を進めてきた知見を活かし、当分野のビジネスに関して多数のクライアントへ法的アドバイスを提供しています。2022年には、ブロックチェーン・暗号資産・NFT・メタバースなどのWeb3分野を専門的に取り扱うチームを立ち上げ、より専門的なサービスを提供できる体制を整えています。
スポットでの相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
*1:https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20250122.html

