重要性が増す、パブリックアフェアーズ。『企業法務のための規制対応&ルールメイキング』の執筆者が語る、官民の相互連携の事例とポイント

Attorney admitted in Japan
Hisako Takahashi
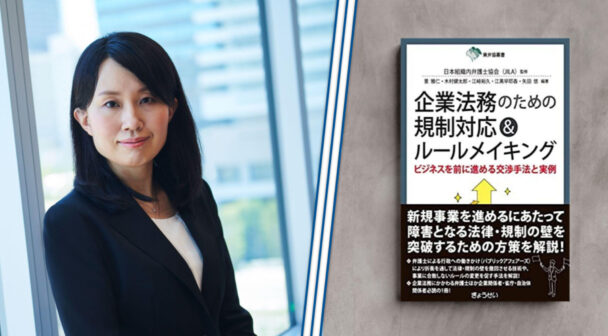
法律事務所ZeLoの結城東輝弁護士が、著書『ルールメイキングがビジネスを制する 勝つ企業の「戦略法務」』(NewsPicks Select)を2021年11月19日に出版します。経営者やビジネスパーソン、法務部に配属されたばかりの方々へ向けて、現代の戦略法務やルールメイキングについて解説した一冊です。本書を執筆するにあたっての問題意識、特におすすめしたいポイント、今後の企業法務に求められる変化について、同弁護士に聞きました。

Graduated from the Faculty of Law, Kyoto University in 2014. the School of Law at Kyoto University and passed the National Bar Examination in 2016. Registered as a lawyer in 2017 (Daini Tokyo Bar Association). Joined ZeLo in 2018. In 2019, joined SmartNews, Inc. While engaging broadly in strategic legal affairs with a focus on law, politics, and technology, he also pursues research on the potential and responsibilities of information. Certified The Advanced Protection of Individual Information Person. Served as an observer member of the Ministry of Justice’s “the Council on Renovation of the Legal and Prosecutorial Administration” (2020). Currently serves as Outside Audit & Supervisory Board Member of STORES, Inc. and TO Books, Inc. Publications include "Strategy and Practice of Rulemaking" (Shojihomu, 2021), among others.
目次
戦略法務、そしてルールメイキングといった概念について、定義や考え方を基本から説明しています。これらの活用がビジネスにおいて不可欠な時代になっていくことを、実例も交えながら解説したものとなります。
本書の執筆にあたっては、法曹実務家ではなく、経営者やビジネスパーソン、法務部に配属されたばかりの方々を意識していました。とにかくシンプルな説明を心がけ、ページ数も抑えたため、少ない時間で本質を理解されたいビジネスパーソンにぜひ届けたい一冊となっています。
昨今、「戦略法務」や「ルールメイキング」といった言葉を至るところで聞くようになりました。少し前は法律家の周辺のみで語られていた言葉が、市民権を得始め、民間企業や官公庁の方々も意識し始めていると思います。
これらの概念が、法律家が発展の可能性を模索し育む「揺籃期」から、いよいよ他のステークホルダーへの浸透が始まる「萌芽期」を経て、その利活用が競争上急務となる「成長期」へと移行する過渡期にあるのではないでしょうか。この過渡期においては、様々な人間にFOMO(Fear of Missing Out、取り残されることへの恐れ)が生まれ、とにかく端的な概念を理解したいと考える方が増えていきます。
当事務所も、まだまだこの分野が成長期前であることを意識しながら、野心的にもその体系的整理に挑戦し、2021年3月に『 ルールメイキングの戦略と実務 』(商事法務)を上梓させていただきました。とはいえ、ビジネスパーソンにとってはそれほど手の届きやすい値段でないことも事実。どのようにして、より多くの「非法律家」に届けようかと悩んでいたところ、NewsPicks様から戦略法務やルールメイキングをテーマにした連載企画をご提案いただき、同企画が好評だったため、この度書籍化いただいたという経緯となります。

「戦略法務」を私なりに噛み砕き、抽象と具体を行き来しながら説明させていただいたのが第一章で、ひときわ思い入れの強いパートです。この章を読んでいただければ、普段契約書を取り扱う法務部・管理部門にいらっしゃる方はもちろん、経営層の方々にとって、「法務がコストセンターではなくプロフィットセンターになる」理由を理解していただけるのではないかと思います。
また、「ルールメイキング」については第三章、第四章で扱っていますが、いずれも実例を中心に解説しています。「ルールメイキング」はよく耳にするけれど、実際何をするのかよくわからないというお声をよく聞きますが、本章を読んでいただければきっと具体的な実務の肌感覚を持っていただけると信じています。特に第四章は、実際に私が扱った事例を読者と一緒に考えていく形式になっていますので、お楽しみいただければ幸いです。
【本書の目次】
出典:『 ルールメイキングがビジネスを制する 勝つ企業の「戦略法務」 』より引用
第一章 教養としての「法務」
第二章 「大企業・スタートアップ連携」に潜むワナ
第三章 新規事業成功のカギ「ルールメイキング」
第四章 「攻めの法務」実際はどのように進むのか?
NewsPicks様から頂戴した企画であったため、読者の対象は、法曹実務家ではなく、経営者やビジネスパーソンや法務部に配属されたばかりの方々だと考えていました。したがって、法律家では当然のように扱う言葉にも、丁寧な説明を加えたり、たとえ話を色々と差し込んだりする形で、退屈な内容にならないよう工夫しました。
具体例を多く敷き詰めた理由は、実際に明日から使えるナレッジを共有したいと考えたためです。抽象的な理想論は耳に聞こえは良いですが、「それでは明日から何をすればいいの?」という疑問を生むことも事実です。多忙なビジネスパーソンにとっても、翌日から同僚や上司、部下に説明が可能になる内容とすべく、身近な具体例を多く記載させていただきました。
企業法務は、しばしば組織の管理部門、ブレーキ役として、リスクを管理し、事業を守る「ガーディアン」としての役割が強調されがちです(あるいはそれしか意識されません)。しかし、経済産業省が公表した「 国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会報告書 」(2019年11月19日)では、「事業の創造」つまりは「価値の創造」に重点を置く「パートナー」としての役割も重視されることが指摘されています。
変動が激しく不確実で複雑かつ曖昧な世界の中で、法が果たすべき役割が急激に変化しているのであれば、それを扱う法務も大きな変化が必要です。変動への柔軟性、不確実性へのレジリエンス、複雑性への対応力、曖昧性への好奇心と発想力、これらを存分に活かしきる企業法務が真価を発揮していく時代になると思います。
ぜひ一人でも多くの方が「戦略法務」に刺激を覚えてくださり、それぞれが従事する事業を成長させる「価値の創造者」になっていただければこれほど嬉しいことはございません。そして、世の中にはそういった野心的な挑戦に興奮を覚える法律家がたくさんいます。ぜひ業界や分野を超えて、共に社会を前進させる当事者となれれば幸いです。
(写真:川村 将貴、編集:村上 未萌)
※記事の内容は掲載当時のものです(掲載日:2021年11月18日)
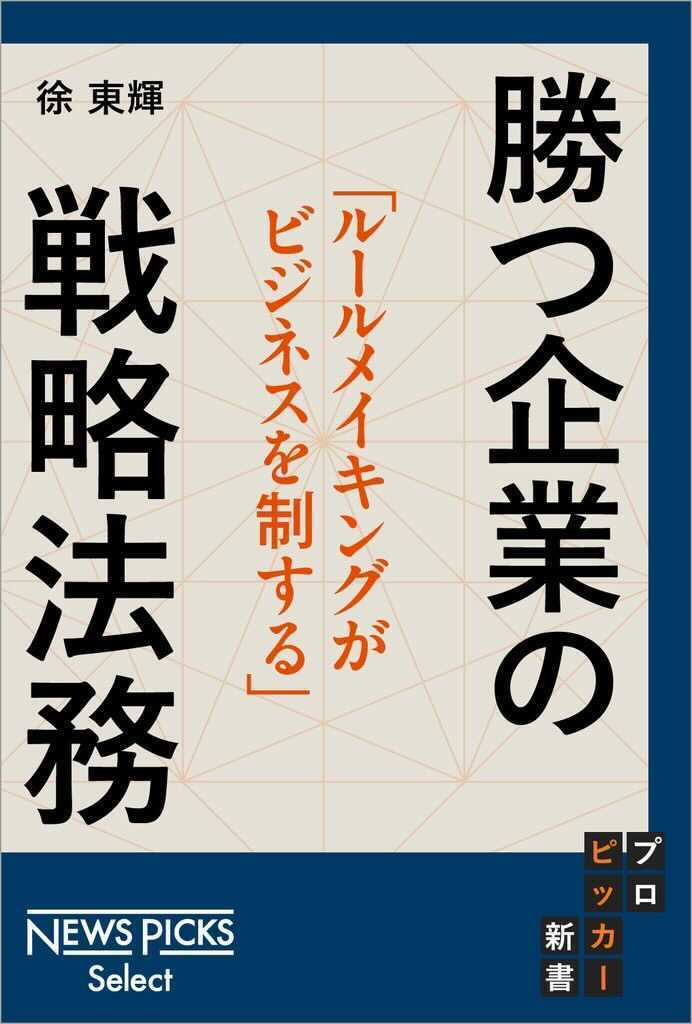
ルールメイキングがビジネスを制する 勝つ企業の「戦略法務」

